- 【2025年6月】栄養科だより
- 【2025年5月】栄養科だより
- 【2025年4月】栄養科だより
- 【2025年3月】栄養科だより
- 【2025年2月】栄養科だより
- 【2025年1月】栄養科だより
- 【2024年12月】栄養科だより
- 【2024年11月】栄養課だより
- 【2024年10月】栄養課だより
- 【2024年9月】栄養課だより
- 【2024年7月】栄養課だより
- 【2024年6月】栄養課だより
- 【2024年5月】栄養課だより
- 【2024年4月】栄養課だより
- 【2024年1月】栄養課だより
- 【2023年12月】栄養課だより
- 【2023年11月】栄養課だより
- 【2023年10月】栄養課だより
- 【2023年9月】栄養課だより
- 【2023年8月】栄養課だより
- 【2023年7月】栄養課だより
- 【2023年6月】栄養課だより
- 第16回
当院行事食について - 第15回
腸内環境と健康 - 第14回
魚の栄養 - 第13回
痛風とプリン体について - 第12回
骨粗鬆症と食事 - 第11回
当院栄養講座開催 - 第10回
風邪予防と食事 - 第09回
夏の水分補給について - 第08回
飲酒について - 第07回 揚げ物の
カロリーダウンのコツ - 第06回
高血圧の食事療法 - 第05回
熱中症と食事 - 第04回
コレステロールについて - 第03回
四季の旬の食材 - 第02回
さつま芋の栄養と調理法 - 第01回 胃腸の働きを
良くする食材とレシピ
食のコラム
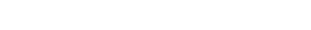
これ以前の記事
これ以前の記事
- 【2026年1月】栄養課だより
- 【2025年12月】栄養課だより
- 【2025年1 1月】栄養課だより
- 【2025年10月】栄養課だより
- 【2025年9月】栄養課だより
- 【2025年8月】栄養課だより
- 【2025年7月】栄養科だより
- 【2025年6月】栄養科だより
- 【2025年5月】栄養科だより
- 【2025年4月】栄養科だより
- 【2025年3月】栄養科だより
- 【2025年2月】栄養科だより
- 【2025年1月】栄養科だより
- 【2024年12月】栄養科だより
- 【2024年11月】栄養課だより
- 【2024年10月】栄養課だより
- 【2024年9月】栄養課だより
- 【2024年7月】栄養課だより
- 【2024年6月】栄養課だより
- 【2024年5月】栄養課だより
- 【2024年4月】栄養課だより
- 【2024年1月】栄養課だより
- 【2023年12月】栄養課だより
- 【2023年11月】栄養課だより
- 【2023年10月】栄養課だより
- 【2023年9月】栄養課だより
- 【2023年8月】栄養課だより
- 【2023年7月】栄養課だより
- 【2023年6月】栄養課だより
- 第16回
当院行事食について - 第15回
腸内環境と健康 - 第14回
魚の栄養 - 第13回
痛風とプリン体について - 第12回
骨粗鬆症と食事 - 第11回
当院栄養講座開催 - 第10回
風邪予防と食事 - 第09回
夏の水分補給について - 第08回
飲酒について - 第07回 揚げ物の
カロリーダウンのコツ - 第06回
高血圧の食事療法 - 第05回
熱中症と食事 - 第04回
コレステロールについて - 第03回
四季の旬の食材 - 第02回
さつま芋の栄養と調理法 - 第01回 胃腸の働きを
良くする食材とレシピ
【2025年2月】栄養課だより
2月といえば“節分”!!
*節分の由来
節分は、中国が発祥とされており、古くから季節の変わり目には邪気が入り、悪いことや予期せぬことが起こりやすいと考えられていたことから、“邪気を払い無病息災を願う目的” に行われていたと言われています。その邪気を “鬼” と考えられており、“鬼は外、福はうち” という掛け声とともに豆をまき邪気を祓い、福を呼び込む行事として今でも行われています。
*なぜ2月に行われるのか
節分という言葉には、季節を分けるという意味があり、本来は季節の始まりの日である二十四
節気の “立春、立夏、立秋、立冬の前日” のすべてを指しています。
現在使われている新暦では1月1日になると新年を迎えますが、旧暦では現在の立春を境に新年が始まっていたため、春の節分は大晦日に当たる特別な日であり、春の節分だけが行事として残るようになったという説があります。
*炒った豆を使うって本当?
基本的には大豆を使用しますが、炒り豆にするのは、後から芽が出てこないようにするため、と言われています。芽が出たら “凶事が起こる” などと、昔の人は恐れたと言います。
新潟県、福島県、北海道などの北日本では、雪深い地域では、外にまかれた豆が雪に埋もれ拾うのが大変、という理由から “落花生” を使用することも多く、地域によっては、 “でん六豆” なんてところも・・!
*なぜ恵方を食べるのか
節分の日に恵方を向いて願い事をしながら恵方巻き(太巻き寿司)を食べると願い事が叶う,縁起が良いと言われている風習です。恵方とは、その年の福をつかさどる歳徳神(としとくじん)がいる、その年の最も縁起の良い方角とされており、恵方に向かって行うことは全て吉となるとされます。また、1本巻なのは “縁を切る” ことがないように、無言で食べるのは “話すと縁が逃げていくから” と言われています。
今年の方角は、西南西でした。 意味を知って行うことでさらに楽しい行事になるかもしれません。
早めの花粉症対策・・
花粉は種類や、時期によってピークが変わりますが、関東では季節を問わず、多くの種類の花粉が飛んでいるのが特徴です。春先にピークがくるスギやヒノキ科だけではなく、秋のブタクサ属をはじめ草本花粉の時期も長いです。花粉症かも?と思ったら、早めの対策が大切です!
*花粉症の方に、おすすめの食べ物
・乳製品 (腸内環境を整えることで、免疫力アップ,アレルギー症状緩和に繋がる)
・食物繊維が豊富な食べ物 (腸内の善玉菌のエサになり、腸内環境を整える)
・青魚 (花粉症などのアレルギー症状を軽くする働きが期待できるDHA,EPAが含まれる)
・チョコレート (カカオポリフェノールには、アレルギー症状を抑える効果がある)
・緑茶 (ポリフェノールの一種であるカテキンが含まれている)
献 立 紹 介

今回は行事食ではなく、日頃から提供している献立の紹介です。
当院では味だけでなく、見た目も重視しており、
特に麺類や丼物は、患者様も職員さんからも
大変喜ばれています。
Menu(2/4)
* オムライス
* 白菜とりんごのサラダ
* コンソメスープ
* ジョア

